自己否定の始まり/ルール編
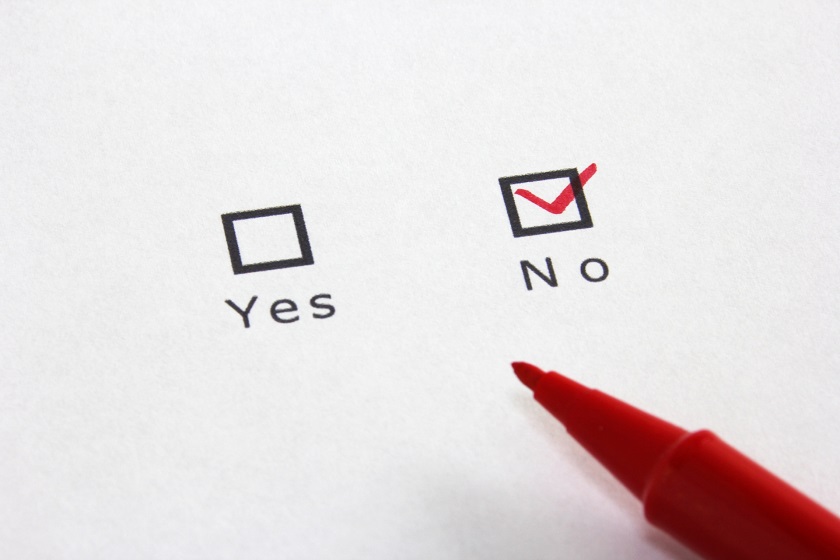
子供も大人も組織に属しているとルールに縛られる面が多々あります。これは学校や会社はもちろん、家や地域、文化や風習も属していれば同じです。今日の話は、そのルールが自己否定を引き起こす過程について。
多くの人が勘違いしていることに、「ルールは正しい」という認識があります。決められたことだからとか、以前からそうだとか、~の立場なら当たり前とか・・・そんな風に思って受け入れていること、多くないですか?そうなると、嫌だ!やりたくない!と思っても仕方なく受け入れたり、多分自分には無理だろうなと思いつつ実行することもあるでしょう。
さて、そんな風に後ろ向きに受け入れたルール。予想通りできなかったり、苦痛で断念すると、ある思考が生まれがちです。「自分が悪い」「自分のせいで」「ダメなのは自分」「私がもっとちゃんとしていれば」・・・そう、自己否定型の思考ですね。思い当たる人は、この先も読んでみてください。
この自己否定、ルールは正しいという思い込みから生まれたものです。正しいことができない→自分は間違っている、という流れですね。しかし考えてみてください。本当にそのルール、正しいですか?もちろん、理にかなったルールもあるでしょうが、中には現状や環境、時代に合わないものも多いはず。あなたが初めに、嫌だな、できないかも、という感想を持ったということは、自分に問題があるからという理由だけではなく、理にかなっていない、意味がわからない、腑に落ちないといったような理由もあるのではないですか?
正しくないルールに振り回されるのは変な話ですよね?だから、ルールに疑問を感じたときは必ずそれについて検討し、可能ならば誰かと意見交換しましょう。ただ受け入れるのではなく、考えをはっきりさせたうえで受け入れるかどうか決める。そうすれば、強制ではなく選択になるからです。(心理実験では、選んで受け入れた嫌なことは、強制された嫌なことよりもストレスが少ないことが実証されています。)
更に、できなかったときに生まれる思考も「やれるだけやった」「今回は仕方ない」といった合理的な自己肯定型になりやすい。正しいから受け入れたのではなく、問題もあるけど話し合いの結果やってみた、という立場に立てるからです。
立場や状況によっては、難しい場合もあるでしょうが、ルールが正しいとは限らないことは、頭の片隅にしまっておいてください。強制より選択です。よりよく生きられるよう工夫していきましょう。
ではまた会う日まで、お元気で。
※愛着の問題を抱えていたり、CPTSD(複雑性トラウマ)の傾向がある場合、無意識に従っているルールや価値観の多くは、親の影響で植え付けられたものとも考えられます。その場合、親の影響力の強さの為、ただ取捨選択することはかなり難しいので、一旦自己理解を進めて自分の価値観を再構築した後で実施することをお勧めします。
関連記事 ⇒ リフレイムの心理カウンセリングについて
関連記事 ⇒ オンラインカウンセリング
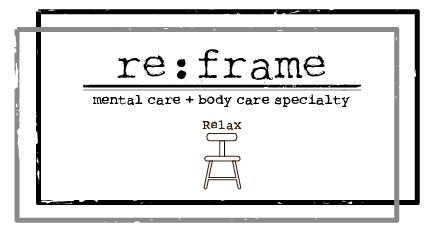





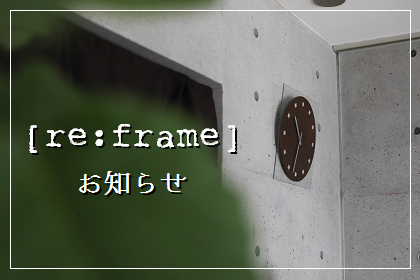
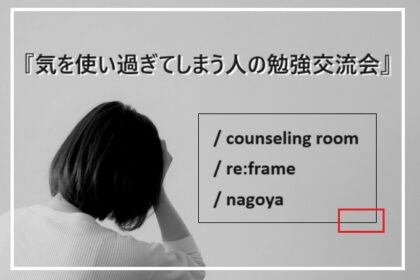


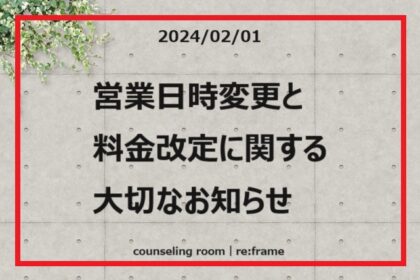

コメントを残す